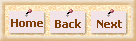あのころのこと
12.二月の空を見上げて
12.1 交換日記 (1996年 2月)
12.2 強い娘 (1996年 2月)
12.3 灰色の雲 (1996年 2月)
交換日記
慢性肺疾患のあみかは、生後5ヶ月を過ぎてようやく保育器から出ることができたとはいうものの、依然として、病院のコットの中で経鼻カテーテルで酸素を補ってもらいながら生きている状態だった。この状態が安定すれば、カテーテルつきで、自宅で生活することが可能になる。だから、多くの場合、慢性肺疾患の子どもは、自宅で酸素ボンベにつながったままで暮らすことを前提に、退院して行く。
あみかもそんな状態だった。主治医からは、
「酸素ボンベをひきずって暮らすようになるかもしれませんね。まあ、今後の経過次第ですが。」
と言われていた。
無理をすれば、この時点であみかを退院させることは不可能ではなかった。けれどこのころ、のぞみは目の手術を繰り返さねばならなかった。TH大学病院に入院するのぞみのところへ、私は毎日付き添いに出かけていた。家であみかを育てられるわけがないのだ。そんな私の窮状とあみかの状態を考慮し、ある程度生活が落着くまで、あみかをT産院に入院させておくという決断は、T産院の好意でもあったし、私はT産院に感謝していた。
にもかかわらず、T産院へあみかの面会に行ったとき、Y看護婦から追いたてられるようにされたことは、思いがけないことだった。このとき、Y看護婦を恨む気持ちがなかったといえば、嘘になる。もちろん、そのことで、T産院と争うようなつもりはなかった。ただ、私の寂しい気持ちを知っておいて欲しいと思っていた。だから、担当の看護婦さんとの交換日記に私はこう書いた。
「先日の面会は、つらい思いでいっぱいで、
帰りの車では涙がとまりませんでした。
あみかとできるだけ長くいたいと思っても、
無理なことはことはわかっているのですが…。
このまま、家に引き取ることができたら、
どんなにいいかと思います。
けれど、今はのぞみの付き添いのため、
午後は毎日TH大学病院へ通わなければなりません。
あみかの面会に毎日行きたくても無理だし、
たとえ引き取っても、私が家でずっとみてやれるわけではありません。
T産院で預かっていただくことが最良の選択なのだ、
とわかってはいても、寂しさがつのります。
みなさまには、本当にお世話になっていて、
いつもありがたいと思っています。
どうぞこれからも、よろしくお願いいたします。」
この日記を、私はT産院に行く夫に託した。
書いたからといって、どうなることも期待したわけではなかった。あみかはY看護婦にかわいがってもらい、T産院でたいせつにされている。私のエゴで無理に連れて帰ることには、なんの意味もない。この選択が、一番いいのだ。これしかないのだ。…私はそう考えていた。
ところが、事態はどんどん変わりつつあった。
(つづく)
ページの先頭に戻る メニューに戻る
強い娘
どうやらあみかは、T産院始まって以来かもしれないくらいの、たいへんな未熟児だったようだ。なにがたいへんなのかは、そのその泣き方を見れば、誰でもすぐにわかっただろう。
「大体、生まれたときから、その子の性格がなんとなくわかるんですよ。」
と、主治医はよく話していたが、誰もが想像するとおり、あみかは相当気が強い性格だったようだ。
その気の強さと根性で、あの、たいへんな胸の痛みと戦い、彼女は生き抜いたのだ、と、私は今でも信じている。だから、気が強くてけっこうじゃないか、と私は思っていた。
ところが、保育器から出してもらって、思う存分、手足を伸ばした暮らしになったら、その気性にはさらに磨きがかかったようだった。あみかは、「だれかに抱いてもらうまで、激しく泣き続ける」という作戦に出たのだ。
あかちゃんだから、泣くのはあたりまえなのだが、その泣き方がハンパじゃなかったらしい。身をよじって、そりかえって、このまま脳の血管が切れてしまうのではないかと思うほど泣き続けるのだ。それは、赤ちゃんのプロであるはずの未熟児室の看護婦さんたちが、とてもじゃないけど放ってはおけない、と思うくらいの激しさだった。
慢性肺疾患のあみかは、呼吸が不安定だ。あまり激しく泣き続けると、酸素が足りなくなり、チアノーゼを起こして、顔が紫色になってしまう。仕方なく、看護婦さんはあみかを抱き、そして抱き続けることとなってしまっていた。
そのころ、面会に行った私に、主治医はこう語っている。
「あみかちゃんのために、看護婦ひとりがはりつき状態になっています。本当にすごい泣き方なんです。」
「お世話になります…。」
と、口では言いながらも、私は内心、「えらいぞ、あみちゃん!」と思っていた。
そのころ、あみかは生後5ヶ月を過ぎていたのだ。普通に生まれていたら、5ヶ月間ずっと、母親にあやされ、抱きしめられ、話しかけられていたはずだ。けれどもあみかは、呼吸器を挿管され、からだを保育器内に固定されて、新生児期のほとんどを過ごしていた。
生きて行くためには、それは仕方のないことだった。命が最優先なのだ。けれども、だんだん命の心配がなくなっていくと、私は次第に、別のことが気になってきた。それは、こんなふうに、母親に抱かれることもなく、家庭の温かさを知らないで育って行くと、どんな子どもになるのだろうか、という不安だった。
それでも私は、「そんなふうに育たざるをえなかったのだから仕方がないのだ、退院してから一生懸命育てればいいのだ。」と自分に言い聞かせてやりすごしてきた。
ところがあみかは、それを自分で解決してしまった。愛情が欠如した状態で育つのではないかという私の心配をよそに、あみかは必死でぬくもりを求めた。そして、激しく泣く、というあみかならではの方法を駆使して、自力で自分用の看護婦さんを確保してしまったのだった。
そんなあみかに、看護婦さんたちも、けっしていやな顔をすることはなかった。ある夜など、他のあかちゃんのケアで手が離せないときに、あみかが泣き始めたことがあったそうだ。そのとき夜勤だった看護婦さんは、なんと、あみかを自分の背中にくくりつけ、仕事を続けてくれたそうだ。
「あみかちゃん、背中に背負っちゃいましたよ〜。」
と明るく語ってくれた若い看護婦さんの顔を、私は今でも鮮やかに思い出す。
これほど気性の激しい子を育てるのはさぞかしたいへんだろう、と心配したのか、
「あみかちゃんを家に引き取って育てるのは、相当の覚悟がいりますよ、おかあさん。」
と、主治医だけは真剣な面持ちで話してくれたが、私は全然平気だった。ほんとうにたいへんかどうか、やってみなければわからないのだから、と思っていた。
そしてあみかには、特別に目をかけてくれているらしいY看護婦もついていた。とにもかくにも、T産院に預かってもらっているあいだは安心だ、と私は思っていた。
そんなあみかに、異変が起こった。
それは、夫に交換日記を託してから、次の週末に私が面会に行ったときのことだった。
未熟児室にはいってきた私の姿を見たときから、看護婦さん達のようすが少し違っていたように思う。そして、あみかのコットに行き、あみかを抱き上げた私に、ひとりの看護婦さんがこう話し始めた。
「あみかちゃん、ミルクを飲まなくなったんですよ…。」
意外なことばだった。気が強くて元気いっぱいだったはずなのに。
「それに寝ないし、抱っこしても泣き止まなかったり…。」
あみかになにがあったのだろう。私は、答えることばがみつからなかった。
そこへ、別の看護婦さんもやってきて、こう言った。
「まあ。あみかちゃん、安心した顔しちゃって。やっぱりおかあさんといっしょにいるのが一番なのよね…。」
そうなのだろうか。
そのことばをすんなりと受け入れるには、私はあまりにも長い間、あみかと離されすぎていた。あみかにとっては、私よりも看護婦さん達の方が、ずっと身近な存在なのではないだろうか。そんなことを考えながら、私が黙って抱いていると、看護婦さんがミルクを持って来てくれた。
「おかあさん、ミルクをあげてみてください。」
ほんの少し前に、どんなにあげたくても許してもらえなかったミルクを、その日は看護婦さんの方が待ちかねたように持って来てくれた。私が哺乳瓶を受け取り、あみかの口にふくませると、あみかはゆっくりと飲み始めた。「看護婦ひとりがはりつき状態」とまで言われている子どもとは思えないほど、その日のあみかはおとなしく、私の腕に身を委ねていた。
「あらあ。おかあさんだと、ミルクをよく飲みますね。よかった。あみかちゃん、おちついて…。おかあさん、面会時間を少しくらい越えていいですから、今日はあみかちゃんのために、ゆっくりいてあげてくださいね。まあ、他のおかあさんの目もありますから、あまり長くはできないんですけど…。」
たしかに、理由はどうあれ、誰もが15分だけで我慢して未熟児室を出て行くのに、私だけがずっと居座っているわけにはいかなかった。少し長めに、と言ってもらえるだけでも、ありがたいことだった。
あみかを抱きながら、私は途惑っていた。あみかは、本当に私のことを母として求めてくれているのだろうか。もしかしたらこれは、交換日記を読んだ看護婦さんたちが、私のために仕組んでくれたことなのではないだろうか、と…。
けれど、私はすぐに考えるのをやめた。そんなこと、どうでもいいことだと思ったのだ。私があみかを抱いて、時間を気にせずにここに座っていることを許されるのなら、理由なんてなんでもよかった。
看護婦さんは、さらにこう付け加えてくれた。
「おかあさん、のぞみくんの面会のためにこちらの面会時間に来ることができないのなら、朝でも夜でも、おかあさんの来られる時間に来てくださっていいですよ。面会時間外なら他のおかあさん方もいませんから、時間を気にせず長い時間いてもかまわないですし…。」
私はびっくりした。そんなことが可能だったのか…。そうであれば、あみかのために、もっと早くそうしていればよかった、と思った。だから、迷わずこう言った。
「それでは、午前中に来させてください。それなら、お昼までにここを出て、3時までにTH大学に着くことができますから。」
「わかりました。それでは、いらっしゃるときは、事前にお電話ください。あみかちゃんを『おふろ』にいれないで待ってますから、おかあさん、いれてあげてくださいね。ほかになにか、ご希望はありますか?」
少し考えてから、私はひとつだけ希望を述べた。
「毎日来てもいいですか?」
なんだか、いきなりうれしいことがいっぱいになってしまった。
今日はミルクをあげて、少し長めに面会させてもらえた。それだけでも大イベントだったのに、明日からはおふろにも入れさせてもらえるのだ。おふろだ、ミルクだ、と私はわくわくしてきた。
そのとき私は気がついた。自分専用の看護婦さんを自力で確保してしまうほどの強い娘だったあみかが、今度は私のことまで自力で呼び寄せてくれたのかもしれない、と。
(つづく)
ページの先頭に戻る メニューに戻る
灰色の雲
翌日から、忙しい毎日が始まった。
一日の間に、朝から晩までかけて、東京都築地にあるT産院と千葉県佐倉市にあるTH大学病院をハシゴするのだ。どちらかひとつに行くだけでも半日仕事だったのだから、一日に両方を、となると、一日中走りまわっているような、忙しい日々になる。たいへんだ、と思う前に、私はすっかりはりきっていた。私の子どもは、ふたりなのだ。毎日ふたりともの顔を見るのはあたりまえのことだった。そんなあたりまえのことが、やっとできるようになったのだ。
毎朝8時に、夫は出勤していく。その後、私は身支度をし、9時に家を出る。中央区までバスや地下鉄を乗り継ぎ、T産院に着くのは10時半だ。
午前中に面会に行くことは前日に言ってあるので、看護婦さんはあみかの沐浴を「とっておいて」くれた。沐浴は、もう手馴れたものだった。一足先に12月に退院していたのぞみを毎日おふろにいれていたのだから、あたりまえのことだ。
私は、余裕であみかの沐浴をすました。そして沐浴のあとは、あみかを抱っこし、ミルクだのおむつだのと、小一時間ほどをいっしょに過ごすことができた。
「のぞみくんは元気ですか?」
と話しかけてくれる看護婦さんもいて、あみかを抱っこしたまま、おしゃべりをすることもあった。
T産院を出るのは12時前ごろだった。地下鉄を乗り継いで、今度は京成上野駅へと向かう。ここから、「特急成田空港行き」が一時間に一本出ていた。こんなものに乗るのは、海外旅行に出かけるときだけだと思っていた。思わず苦笑してしまう。
それを利用しても、TH大学病院の最寄り駅である「ユーカリが丘」駅までは一時間かかった。そして、「ユーカリが丘」駅からTH大学病院までは、さらにバスを利用しなければならない。昼食は、移動時間の合間に簡単なものを買って済ませた。ゆっくりとどこかの店にはいって食事をとるほどの時間はなかったし、そうしたい気持ちにもならなかった。
こうして電車やバスを乗り継いで、TH大学病院の小児科に着くころには2時半を過ぎていた。面会時間は3時からだったが、少しくらい早めに入室しても、看護婦さんは目をつぶってくれた。
病室のベッドで寝ているのぞみを抱っこすると、あとは、6時半の最終バスがでるまで、のぞみに歌を歌ったりミルクを飲ませたりして過ごす。それは、一日の中でいちばんゆったりとした時間だった。
病院を出る最終バスに乗ると、船橋市にある自宅に帰り着くのは8時になる。既に十分遅い時間だったが、その時刻から、私は夕食の支度を始めた。夫が帰宅するのはせいぜい9時だったので、夕食までにはまだ時間がある。
毎晩、夜9時ごろに夫が帰ってきて、入浴・食事…というのが、我が家のふだんの生活だったから、私が昼間いくらあちこちに飛びまわっていても、夜帰宅してからの生活にはなんの変わりもなかった。
考えてみたら、出産するまでは私も仕事をしていて、家に帰り着くのはいつも7時半を過ぎていた。それから食事の支度を始めていたのだから、以前の生活と大差はなかったことになる。つまり、日中会社に行っていたはずの時間を使って、そのまま病院に行っているだけなのだ。当時の私は「育児休職中」であったが、「一日中子どもの面会で、これではまるで、『介護休職中』みたいなもんだ。」とおかしくなった。
夫と夕食をとりながら、その日の子どもたちの様子を話す。ウンチがどうだったとか、ミルクが多かったとか、たわいのないことばかりだ。それなりに穏やかで、幸せな生活だった。
このころのことを思い出すとき、私の心に浮かぶのはいつも、頭上に広がっていた灰色の空だ。二月とはいえ、晴れの日も雨の日もあったはずなのだ。けれど私が思い出すのは、なぜか、どこまでもひろがっていた曇り空だ。
数えてみると、毎日、のべ6時間以上を電車やバスに乗り継いで過ごしていた。自宅、T産院、そしてTH大学病院を行き来しながら、私の頭の中は、のぞみとこれからどう生きていこうか、という思いでいっぱいだった。そして、電車の座席で目を閉じては、毎日、毎日、過ぎていった様々なできごとを私は反芻していた。私を懸命に支えようとしてくれている実家の家族のこと、私たちから逃げていった夫の両親のこと、そして、多くの友人のこと…。
昼間の人気の少ない車内で、気がつくと私はいつも泣いていた。毎日、毎日、同じことを思い返しては涙を流していた。そうしてひとしきり泣いて目をあけると、窓の外には、どんよりとした灰色の雲がどこまでも広がっていた。ほんの少しだけ差し込んでいる薄日のせいで、冬の寒々しい曇り空はわずかながらの温かみを帯びている。それは、2月の空とは思えないほど優しく目にしみた。
一日の四分の一強を移動時間に費やし、一日の二分の一を子どもの面会のためだけに過ごす生活だったが、それをつらいとかたいへんだと思ったことは一度もなかったと思う。むしろ私は、生きていく「はりあい」を感じていた。考えてみたら、一日の時間のほとんどを子どものために使うのは、赤ちゃんを育てる母親ならばあたりまえのことだ。自分の生活も、少しはその「あたりまえ」に近づけたような気がして、私はうれしかった。
電車に揺られながら、誰にも邪魔されることなく、私はいつも空に広がる雲を眺めていた。そうやって、起こってしまった事を何度も何度も反芻する時期は、現在の私に行き着くまでに、たしかにどこかで必要だったのだと思う。
二月の空を見上げながら、こんなふうにして私は、少しずつ、次の一歩を踏み出す勇気を蓄えていったのかもしれない。
(つづく)
12.1 交換日記 (1996年 2月)
12.2 強い娘 (1996年 2月)
12.3 灰色の雲 (1996年 2月)
交換日記
慢性肺疾患のあみかは、生後5ヶ月を過ぎてようやく保育器から出ることができたとはいうものの、依然として、病院のコットの中で経鼻カテーテルで酸素を補ってもらいながら生きている状態だった。この状態が安定すれば、カテーテルつきで、自宅で生活することが可能になる。だから、多くの場合、慢性肺疾患の子どもは、自宅で酸素ボンベにつながったままで暮らすことを前提に、退院して行く。
あみかもそんな状態だった。主治医からは、
「酸素ボンベをひきずって暮らすようになるかもしれませんね。まあ、今後の経過次第ですが。」
と言われていた。
無理をすれば、この時点であみかを退院させることは不可能ではなかった。けれどこのころ、のぞみは目の手術を繰り返さねばならなかった。TH大学病院に入院するのぞみのところへ、私は毎日付き添いに出かけていた。家であみかを育てられるわけがないのだ。そんな私の窮状とあみかの状態を考慮し、ある程度生活が落着くまで、あみかをT産院に入院させておくという決断は、T産院の好意でもあったし、私はT産院に感謝していた。
にもかかわらず、T産院へあみかの面会に行ったとき、Y看護婦から追いたてられるようにされたことは、思いがけないことだった。このとき、Y看護婦を恨む気持ちがなかったといえば、嘘になる。もちろん、そのことで、T産院と争うようなつもりはなかった。ただ、私の寂しい気持ちを知っておいて欲しいと思っていた。だから、担当の看護婦さんとの交換日記に私はこう書いた。
「先日の面会は、つらい思いでいっぱいで、
帰りの車では涙がとまりませんでした。
あみかとできるだけ長くいたいと思っても、
無理なことはことはわかっているのですが…。
このまま、家に引き取ることができたら、
どんなにいいかと思います。
けれど、今はのぞみの付き添いのため、
午後は毎日TH大学病院へ通わなければなりません。
あみかの面会に毎日行きたくても無理だし、
たとえ引き取っても、私が家でずっとみてやれるわけではありません。
T産院で預かっていただくことが最良の選択なのだ、
とわかってはいても、寂しさがつのります。
みなさまには、本当にお世話になっていて、
いつもありがたいと思っています。
どうぞこれからも、よろしくお願いいたします。」
この日記を、私はT産院に行く夫に託した。
書いたからといって、どうなることも期待したわけではなかった。あみかはY看護婦にかわいがってもらい、T産院でたいせつにされている。私のエゴで無理に連れて帰ることには、なんの意味もない。この選択が、一番いいのだ。これしかないのだ。…私はそう考えていた。
ところが、事態はどんどん変わりつつあった。
(つづく)
ページの先頭に戻る メニューに戻る
強い娘
どうやらあみかは、T産院始まって以来かもしれないくらいの、たいへんな未熟児だったようだ。なにがたいへんなのかは、そのその泣き方を見れば、誰でもすぐにわかっただろう。
「大体、生まれたときから、その子の性格がなんとなくわかるんですよ。」
と、主治医はよく話していたが、誰もが想像するとおり、あみかは相当気が強い性格だったようだ。
その気の強さと根性で、あの、たいへんな胸の痛みと戦い、彼女は生き抜いたのだ、と、私は今でも信じている。だから、気が強くてけっこうじゃないか、と私は思っていた。
ところが、保育器から出してもらって、思う存分、手足を伸ばした暮らしになったら、その気性にはさらに磨きがかかったようだった。あみかは、「だれかに抱いてもらうまで、激しく泣き続ける」という作戦に出たのだ。
あかちゃんだから、泣くのはあたりまえなのだが、その泣き方がハンパじゃなかったらしい。身をよじって、そりかえって、このまま脳の血管が切れてしまうのではないかと思うほど泣き続けるのだ。それは、赤ちゃんのプロであるはずの未熟児室の看護婦さんたちが、とてもじゃないけど放ってはおけない、と思うくらいの激しさだった。
慢性肺疾患のあみかは、呼吸が不安定だ。あまり激しく泣き続けると、酸素が足りなくなり、チアノーゼを起こして、顔が紫色になってしまう。仕方なく、看護婦さんはあみかを抱き、そして抱き続けることとなってしまっていた。
そのころ、面会に行った私に、主治医はこう語っている。
「あみかちゃんのために、看護婦ひとりがはりつき状態になっています。本当にすごい泣き方なんです。」
「お世話になります…。」
と、口では言いながらも、私は内心、「えらいぞ、あみちゃん!」と思っていた。
そのころ、あみかは生後5ヶ月を過ぎていたのだ。普通に生まれていたら、5ヶ月間ずっと、母親にあやされ、抱きしめられ、話しかけられていたはずだ。けれどもあみかは、呼吸器を挿管され、からだを保育器内に固定されて、新生児期のほとんどを過ごしていた。
生きて行くためには、それは仕方のないことだった。命が最優先なのだ。けれども、だんだん命の心配がなくなっていくと、私は次第に、別のことが気になってきた。それは、こんなふうに、母親に抱かれることもなく、家庭の温かさを知らないで育って行くと、どんな子どもになるのだろうか、という不安だった。
それでも私は、「そんなふうに育たざるをえなかったのだから仕方がないのだ、退院してから一生懸命育てればいいのだ。」と自分に言い聞かせてやりすごしてきた。
ところがあみかは、それを自分で解決してしまった。愛情が欠如した状態で育つのではないかという私の心配をよそに、あみかは必死でぬくもりを求めた。そして、激しく泣く、というあみかならではの方法を駆使して、自力で自分用の看護婦さんを確保してしまったのだった。
そんなあみかに、看護婦さんたちも、けっしていやな顔をすることはなかった。ある夜など、他のあかちゃんのケアで手が離せないときに、あみかが泣き始めたことがあったそうだ。そのとき夜勤だった看護婦さんは、なんと、あみかを自分の背中にくくりつけ、仕事を続けてくれたそうだ。
「あみかちゃん、背中に背負っちゃいましたよ〜。」
と明るく語ってくれた若い看護婦さんの顔を、私は今でも鮮やかに思い出す。
これほど気性の激しい子を育てるのはさぞかしたいへんだろう、と心配したのか、
「あみかちゃんを家に引き取って育てるのは、相当の覚悟がいりますよ、おかあさん。」
と、主治医だけは真剣な面持ちで話してくれたが、私は全然平気だった。ほんとうにたいへんかどうか、やってみなければわからないのだから、と思っていた。
そしてあみかには、特別に目をかけてくれているらしいY看護婦もついていた。とにもかくにも、T産院に預かってもらっているあいだは安心だ、と私は思っていた。
そんなあみかに、異変が起こった。
それは、夫に交換日記を託してから、次の週末に私が面会に行ったときのことだった。
未熟児室にはいってきた私の姿を見たときから、看護婦さん達のようすが少し違っていたように思う。そして、あみかのコットに行き、あみかを抱き上げた私に、ひとりの看護婦さんがこう話し始めた。
「あみかちゃん、ミルクを飲まなくなったんですよ…。」
意外なことばだった。気が強くて元気いっぱいだったはずなのに。
「それに寝ないし、抱っこしても泣き止まなかったり…。」
あみかになにがあったのだろう。私は、答えることばがみつからなかった。
そこへ、別の看護婦さんもやってきて、こう言った。
「まあ。あみかちゃん、安心した顔しちゃって。やっぱりおかあさんといっしょにいるのが一番なのよね…。」
そうなのだろうか。
そのことばをすんなりと受け入れるには、私はあまりにも長い間、あみかと離されすぎていた。あみかにとっては、私よりも看護婦さん達の方が、ずっと身近な存在なのではないだろうか。そんなことを考えながら、私が黙って抱いていると、看護婦さんがミルクを持って来てくれた。
「おかあさん、ミルクをあげてみてください。」
ほんの少し前に、どんなにあげたくても許してもらえなかったミルクを、その日は看護婦さんの方が待ちかねたように持って来てくれた。私が哺乳瓶を受け取り、あみかの口にふくませると、あみかはゆっくりと飲み始めた。「看護婦ひとりがはりつき状態」とまで言われている子どもとは思えないほど、その日のあみかはおとなしく、私の腕に身を委ねていた。
「あらあ。おかあさんだと、ミルクをよく飲みますね。よかった。あみかちゃん、おちついて…。おかあさん、面会時間を少しくらい越えていいですから、今日はあみかちゃんのために、ゆっくりいてあげてくださいね。まあ、他のおかあさんの目もありますから、あまり長くはできないんですけど…。」
たしかに、理由はどうあれ、誰もが15分だけで我慢して未熟児室を出て行くのに、私だけがずっと居座っているわけにはいかなかった。少し長めに、と言ってもらえるだけでも、ありがたいことだった。
あみかを抱きながら、私は途惑っていた。あみかは、本当に私のことを母として求めてくれているのだろうか。もしかしたらこれは、交換日記を読んだ看護婦さんたちが、私のために仕組んでくれたことなのではないだろうか、と…。
けれど、私はすぐに考えるのをやめた。そんなこと、どうでもいいことだと思ったのだ。私があみかを抱いて、時間を気にせずにここに座っていることを許されるのなら、理由なんてなんでもよかった。
看護婦さんは、さらにこう付け加えてくれた。
「おかあさん、のぞみくんの面会のためにこちらの面会時間に来ることができないのなら、朝でも夜でも、おかあさんの来られる時間に来てくださっていいですよ。面会時間外なら他のおかあさん方もいませんから、時間を気にせず長い時間いてもかまわないですし…。」
私はびっくりした。そんなことが可能だったのか…。そうであれば、あみかのために、もっと早くそうしていればよかった、と思った。だから、迷わずこう言った。
「それでは、午前中に来させてください。それなら、お昼までにここを出て、3時までにTH大学に着くことができますから。」
「わかりました。それでは、いらっしゃるときは、事前にお電話ください。あみかちゃんを『おふろ』にいれないで待ってますから、おかあさん、いれてあげてくださいね。ほかになにか、ご希望はありますか?」
少し考えてから、私はひとつだけ希望を述べた。
「毎日来てもいいですか?」
なんだか、いきなりうれしいことがいっぱいになってしまった。
今日はミルクをあげて、少し長めに面会させてもらえた。それだけでも大イベントだったのに、明日からはおふろにも入れさせてもらえるのだ。おふろだ、ミルクだ、と私はわくわくしてきた。
そのとき私は気がついた。自分専用の看護婦さんを自力で確保してしまうほどの強い娘だったあみかが、今度は私のことまで自力で呼び寄せてくれたのかもしれない、と。
(つづく)
ページの先頭に戻る メニューに戻る
灰色の雲
翌日から、忙しい毎日が始まった。
一日の間に、朝から晩までかけて、東京都築地にあるT産院と千葉県佐倉市にあるTH大学病院をハシゴするのだ。どちらかひとつに行くだけでも半日仕事だったのだから、一日に両方を、となると、一日中走りまわっているような、忙しい日々になる。たいへんだ、と思う前に、私はすっかりはりきっていた。私の子どもは、ふたりなのだ。毎日ふたりともの顔を見るのはあたりまえのことだった。そんなあたりまえのことが、やっとできるようになったのだ。
毎朝8時に、夫は出勤していく。その後、私は身支度をし、9時に家を出る。中央区までバスや地下鉄を乗り継ぎ、T産院に着くのは10時半だ。
午前中に面会に行くことは前日に言ってあるので、看護婦さんはあみかの沐浴を「とっておいて」くれた。沐浴は、もう手馴れたものだった。一足先に12月に退院していたのぞみを毎日おふろにいれていたのだから、あたりまえのことだ。
私は、余裕であみかの沐浴をすました。そして沐浴のあとは、あみかを抱っこし、ミルクだのおむつだのと、小一時間ほどをいっしょに過ごすことができた。
「のぞみくんは元気ですか?」
と話しかけてくれる看護婦さんもいて、あみかを抱っこしたまま、おしゃべりをすることもあった。
T産院を出るのは12時前ごろだった。地下鉄を乗り継いで、今度は京成上野駅へと向かう。ここから、「特急成田空港行き」が一時間に一本出ていた。こんなものに乗るのは、海外旅行に出かけるときだけだと思っていた。思わず苦笑してしまう。
それを利用しても、TH大学病院の最寄り駅である「ユーカリが丘」駅までは一時間かかった。そして、「ユーカリが丘」駅からTH大学病院までは、さらにバスを利用しなければならない。昼食は、移動時間の合間に簡単なものを買って済ませた。ゆっくりとどこかの店にはいって食事をとるほどの時間はなかったし、そうしたい気持ちにもならなかった。
こうして電車やバスを乗り継いで、TH大学病院の小児科に着くころには2時半を過ぎていた。面会時間は3時からだったが、少しくらい早めに入室しても、看護婦さんは目をつぶってくれた。
病室のベッドで寝ているのぞみを抱っこすると、あとは、6時半の最終バスがでるまで、のぞみに歌を歌ったりミルクを飲ませたりして過ごす。それは、一日の中でいちばんゆったりとした時間だった。
病院を出る最終バスに乗ると、船橋市にある自宅に帰り着くのは8時になる。既に十分遅い時間だったが、その時刻から、私は夕食の支度を始めた。夫が帰宅するのはせいぜい9時だったので、夕食までにはまだ時間がある。
毎晩、夜9時ごろに夫が帰ってきて、入浴・食事…というのが、我が家のふだんの生活だったから、私が昼間いくらあちこちに飛びまわっていても、夜帰宅してからの生活にはなんの変わりもなかった。
考えてみたら、出産するまでは私も仕事をしていて、家に帰り着くのはいつも7時半を過ぎていた。それから食事の支度を始めていたのだから、以前の生活と大差はなかったことになる。つまり、日中会社に行っていたはずの時間を使って、そのまま病院に行っているだけなのだ。当時の私は「育児休職中」であったが、「一日中子どもの面会で、これではまるで、『介護休職中』みたいなもんだ。」とおかしくなった。
夫と夕食をとりながら、その日の子どもたちの様子を話す。ウンチがどうだったとか、ミルクが多かったとか、たわいのないことばかりだ。それなりに穏やかで、幸せな生活だった。
このころのことを思い出すとき、私の心に浮かぶのはいつも、頭上に広がっていた灰色の空だ。二月とはいえ、晴れの日も雨の日もあったはずなのだ。けれど私が思い出すのは、なぜか、どこまでもひろがっていた曇り空だ。
数えてみると、毎日、のべ6時間以上を電車やバスに乗り継いで過ごしていた。自宅、T産院、そしてTH大学病院を行き来しながら、私の頭の中は、のぞみとこれからどう生きていこうか、という思いでいっぱいだった。そして、電車の座席で目を閉じては、毎日、毎日、過ぎていった様々なできごとを私は反芻していた。私を懸命に支えようとしてくれている実家の家族のこと、私たちから逃げていった夫の両親のこと、そして、多くの友人のこと…。
昼間の人気の少ない車内で、気がつくと私はいつも泣いていた。毎日、毎日、同じことを思い返しては涙を流していた。そうしてひとしきり泣いて目をあけると、窓の外には、どんよりとした灰色の雲がどこまでも広がっていた。ほんの少しだけ差し込んでいる薄日のせいで、冬の寒々しい曇り空はわずかながらの温かみを帯びている。それは、2月の空とは思えないほど優しく目にしみた。
一日の四分の一強を移動時間に費やし、一日の二分の一を子どもの面会のためだけに過ごす生活だったが、それをつらいとかたいへんだと思ったことは一度もなかったと思う。むしろ私は、生きていく「はりあい」を感じていた。考えてみたら、一日の時間のほとんどを子どものために使うのは、赤ちゃんを育てる母親ならばあたりまえのことだ。自分の生活も、少しはその「あたりまえ」に近づけたような気がして、私はうれしかった。
電車に揺られながら、誰にも邪魔されることなく、私はいつも空に広がる雲を眺めていた。そうやって、起こってしまった事を何度も何度も反芻する時期は、現在の私に行き着くまでに、たしかにどこかで必要だったのだと思う。
二月の空を見上げながら、こんなふうにして私は、少しずつ、次の一歩を踏み出す勇気を蓄えていったのかもしれない。
(つづく)